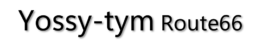健康に多少でも興味を持っている方や、テレビの健康番組でも時折耳にしたであろうロコモ(ロコモティブシンドローム、Locomotive syndrome)、サルコペニア(sarcopenia)、フレイル(frailty、 frailty syndrome)だが、その違いを私はこれまであまり意識したことがなかった。しかし或る日、整形外科主治医からその違いを聞いた時、俄然と興味が湧いてきた。何故なら、私には(罹った病気も含めて)そのいずれもが当てはまるからだ。
ここでは、三つの言葉の違いとその特徴を、簡単に私なりの勝手な解釈で綴ってみたので、興味と時間のある方は読んでいってください。
ロコモとサルコペニア、フレイルの違い
諸説あるかと思われるが、ざっくり言えば「ロコモティブシンドローム」は、運動器障害における整形外科学的アプローチで、2007年に日本整形外科学会により提唱され、対して「サルコペニア」「フレイル」は加齢や疾患、生活習慣や周囲環境などによる身体機能・認知・判断の低下を指し、内科学的で多面的なアプローチとなる。因みに、「サルコペニア」は1989年に提唱され2010年に欧州の研究チームによって定義づけされ、「フレイル」は最近になって日本老年医学会より提唱された用語である。
日本生活習慣病予防協会によれば、ロコモティブシンドロームの国内推計患者数は予備軍を含めて4,700万人と言われ、日本の総人口の約4割を占める。また、フレイルの有病率(※1)は65歳以上の高齢者全体の約1割を占め、400万人に迫る勢いだと思われる。
ロコモティブシンドロームとは?(概要)
公益社団法人日本整形外科学会によれば、ロコモティブシンドロームとは「運動器(※2)の障害のために立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)が低下した状態」で、ロコモが進行すると将来における介護リスクが高くなると言われている。また、ロコモは、運動器不安定症(Musculoskeletal Ambulation Disability Symptom Complex:MADS)の概念となっており、高齢であるとか運動機能の低下をきたす運動器疾患により、バランス能力や歩行(移動)能力の低下が生じ、そのため閉じこもりや転倒リスクが高まり、日常生活での障害を伴う疾患をいう。
なお、詳細については別に紹介するので、そちらを参照していただきたい。
サルコペニアとは?(概要)
一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会などによれば、サルコペニアとは「加齢による筋肉量の減少および筋力の低下のことを指し、歩く・立ち上がるなどの日常生活の基本的な動作に影響が生じ、要介護度や転倒のリスクが高くなる状態」をいう。また、各種疾患の重症化や生存期間にもサルコペニアが影響するとされていることから、現在は様々な分野にまたがって注目されている。
日本では500万人以上の高齢者(65歳以上)がサルコペニアに該当すると言われており、加齢によって有症者は増加し、特に男性に多くみられるなどの特徴がある。
なお、老化によって減少した筋肉であっても、運動と栄養により改善を期待することが出来ることから、筋肉量の減少および筋力の低下を意識するようになった場合には、かかりつけの医師に相談することも必要である。
フレイルとは?(概要)
一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会などによれば、フレイルとは「加齢により心身が衰えた(加齢とともに運動機能や認知機能等の心身の活力が低下した)状態のことで、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能も障害や心身の脆弱性が出現した合併症リスクの一つ」とされているが、一方で「適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」とも言われている。
特に、高齢者において発症しやすいことが分かっているため、介護状態にならないためにもフレイルに早く気付き、正しく対処することが大切だと言われている。
まとめ
共通していることは、加齢や疾病などによる運動機能の低下は将来の介護度を高める原因となるため、筋力の低下など意識するようになった場合は勿論だが、ある程度の年齢に達すれば上記三つの症状を認識し、早めの対処により、将来の要介護度や認知機能の低下を防ぐことができるということではないだろうか。
加齢というものを正しく認識し、正しく対処する。このことが楽しい人生を歩むことになるのでは、と改めて気付いた次第である。
———- + ———- + ———-
※1 有病率:ある一時点において疾病を有している人の割合を言い、集団の特定の時点での健康問題の大きさをはかる指標である。なお、これに関してよく言い表される罹患率とは、一定期間にどれだけの疾病(健康障害)者が発生したかを示す指標で、疾病と発生要因との因果関係を探査する場合に有用な指標である。(一般社団法人日本疫学会「疫学用語の基礎知識」より抜粋)
※2 運動器:身体運動に関する筋、骨格及び神経系の総称で、自分の意志で制御できる唯一の組織・臓器。
参考文献等(外部リンク)
- 公益社団法人日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp
- 一般社団法人日本内科学会 https://www.naika.or.jp
- 一般社団法人日本老年医学会 https://www.jpn-geriat-soc.or.jp
- 一般社団法人日本疫学会 https://jeaweb.jp
- 一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会 https://www.jasf.jp
- 公益財団法人長寿科学振興財団 https://www.tyojyu.or.jp
- 一般社団法人日本生活習慣病予防協会(JPALD、Japan Preventine Association of Life-style related Disease) https://seikatsusyukanbyo.com