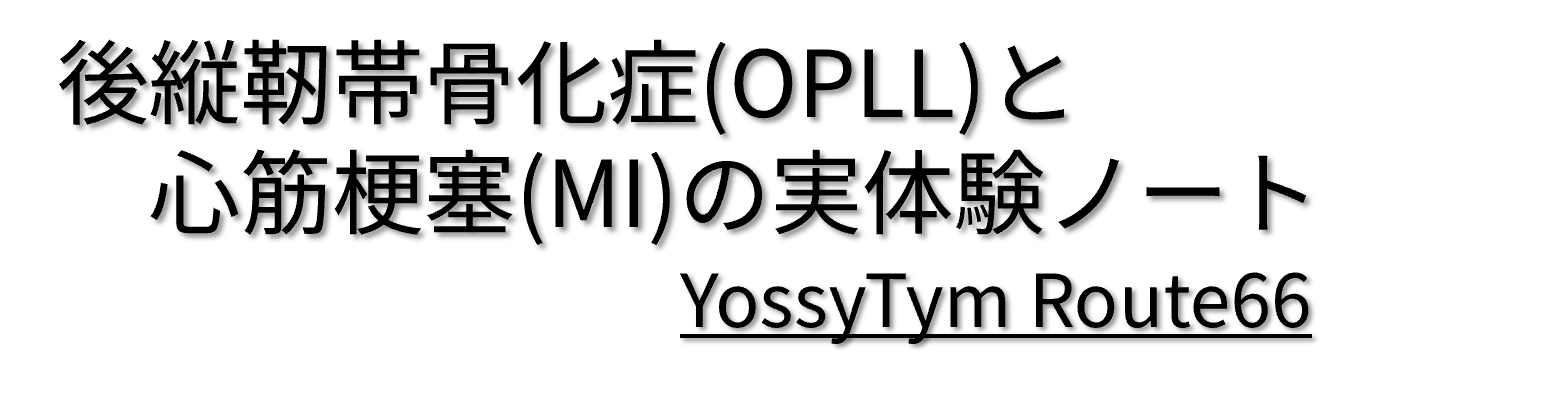2011年(平成23年)8月26日、急性心筋梗塞により緊急手術、入院。
その後、今こうやって記事を書いているということは、私の身体は、日常生活に大きな不都合がない状態だと言えます。
しかし発症当時は、やはり残念な気持ちや後悔もありました。幸いなことに、復帰しようとする気持ちになるまで、それほど時間はかかりませんでしたが、
体力面での回復には相当な時間を要しました。
それでは、当時の話を掻い摘んで書きましたので、お時間のある方はどうぞ読んでいってください。
※医療的注意書き
本記事は、筆者自身の体験をもとにした記録であり、診断や治療を勧めるものではありません。症状や経過、回復の過程には個人差があり、同じ結果が得られるとは限りません。体調に異変を感じた場合や治療・リハビリについては、必ず医師などの専門職にご相談ください。
発症前(受診サイン)~退院直後
心筋梗塞の発症前日|見逃してしまった「受診のサイン」
夏の終わりの週末…この日は朝からとても暑く、私の体調はすこぶる悪かった。胸の圧迫感、浅い呼吸、冷や汗、多少の目まい。おそらく前日から深い睡眠ができていなかった事が原因だと自分に言い聞かせていました。
しかし、その症状は職場に着いてからも改善することはなく、むしろ悪化する一方です。特に胸の圧迫感は、時には鈍痛をわずかに伴い呼吸が乱れるほどになっており、冷や汗も段々多くなってきていました。
その内、集中力が持たなくなり、流石にこの日は職場に着いて間も無く早退することにしたのです。

”心臓の痛みと冷や汗で苦しむ男性のイラスト”
© いらすとや
上司から早退の許可をもらい早速帰路についたのですが、大量の冷や汗と胸痛のため、帰宅途中で何度も車を止め呼吸を落ち着かせることに相当な時間を費やし、家に着くまでいつもより相当長い時間を要してしまいました。
帰宅後はすぐにベッドに入り只々睡眠をむさぼってしまって、気が付くと夕方。残念ながら、目が覚めても症状はあまり改善していませんでした。
「冷や汗は止まったが胸の圧迫感は収まっていない。明日は医者に行こう…」
と決意したのですが、何故この時「今すぐ医者に行こう」と思わなかったのか。この様な症状に陥っても何故まだ大丈夫だと思ったのか、運よくこうやって生きながらえていますが、場合によっては翌日冷たくなっていたかもしれないのです。
この様に「自分は大丈夫だ」という何の根拠も無い屁理屈と、日常から自身の身体を顧みない姿勢が重病を発症させ、症状を悪化させる結果となってしまったことに、もっと早く気付くべきでした。
緊急診断からカテーテル手術(PCI)へ
緊急診断
翌日、妻に病院まで送ってもらい、意識が朦朧とする中で、なんとか外来までたどり着いたのですが内科受付前で力尽き、待合ソファーに倒れ込んでしまいました。近くに居た方が病院スタッフを呼んでくださったらしく、いつの間にか私の周りには白衣を着た方々が取り囲んでいて、ぼんやりとした意識の中で少し安堵していたことが思い出されます。
当時の担当医も直ぐ駆けつけてくれ、血圧、心電図、採血などの検査を受けました。そこで下った診断は「急性心筋梗塞」。緊急手術が必要であることも告げられ、愕然としている私の周囲では手術の準備が慌ただしく始まったのですが、この時、私の耳には周りの音があまり入ってきておらず、所謂「おいてけぼり」状態。これまでの定期診察で「高血圧症」の診断は受けており、ある程度の病名は覚悟していたのですが現実は、私にとって最も重く受け止めざるを得ない診断でした。
病院で「急性心筋梗塞」の診断を受けた当時は、自分はこの後どうなるのか、一生を酸素吸入器などの医療器械や薬に頼らなくてはいけない生活となるのか、また余命は長くないかもしれないなど不安ばかりが脳裏をよぎりました。同時に、異動して間もない職場に大変な迷惑をかけてしまったことや、家族に余計な心配をかけてしまったことに申し訳ない気持ちで一杯でした。
今でも当時の事を思い出して赤面するのは「もう煙草は喫えないのでしょうか。」などと担当医に聞いていたことです。この期に及んでまだ喫煙と縁を切れない自分がいたのです。勿論、医者からの強い忠告もあり煙草はその場でスッパリ止めたのですが、その後身体が復調するにつれ、この喫煙欲求というものに結構悩まされることになるのです。今振り返ると、このような依存の強さこそが、心疾患のリスクを高めていた一因だったのだと思います。
手術と術直後
術式は、カテーテル・インターベンション(Percutaneous Coronary Intervention;PCI/経皮的冠動脈形成術)と言い、左遠位橈骨動脈(左手首)に局所麻酔をして、そこから血管にカテーテルを挿入します。
挿入中は所々でカテーテルの動きを感じることもあり、造影剤が流し込まれた際、ベッド横の大きなディスプレイには私の血管が映し出されていて、それを見ていると何だかSFの世界に迷い込んだような感覚があったのを今でも思い出します。
血管内にカテーテルを梗塞部位まで挿入したら、その位置でバルーンを拡張させ、ステント(3mmΦ×15mmL)を挿入することで、梗塞した血管を拡げた状態に形成します。私の場合、左主冠状動脈が梗塞しており、左回旋枝と左前下行枝への血液は既に滞っていたのですが、運よく心筋壊死部は少なかったので(健全ではないのですが)少しは安堵しました。実は、この心臓へのダメージが放っておいた割には軽く済んだことが、後のリハビリテーションに対し積極的に取り組める理由の一つとなっています。術後はステントの適合状況などを確認するため、ICU(Intensive Care Unit:集中治療室)・HCU(High Care Unit:高度治療室)で二日ほど状態監視されました。
2週間の入院生活と「ベッド上の排泄」という葛藤
緊急手術を終え、高度集中治療室での経過も良かったので一般病室に移ることに。しかし私の身体にはまだ沢山の静脈注射が施されており、自分勝手にベッドから出ることはできないため、個室病室での管理体制となっていました。
ここで一番大変だったのは排泄。無理をしなければ病室内のトイレまでなら十分歩行は可能なのですが、安静状態を保たなければならないことや、何本もの点滴がつながったスタンドを伴って行けないため、仕方なくベッドの上で排泄処理をすることに。これが結構ストレスだったのですが「身から出たサビ」なので文句は言えません。
個室病室で3日間ほど過ごしたあとは多床病室での入院生活。午前中は検査や簡単なリハビリが行われ忙しく過ごしますが、それ以外は原則としてトイレ・入浴以外の行動に制限がかけられていたため、午後からは非常に退屈でした。
9月10日退院。緊急手術から2週間余りで退院できだのですが、屋外に出てみると愕然としました。残暑が厳しかったこともあるのでしょうが、
体力の落ち込みが想定外で酷かったのです。
退院後に直面した「想定外の体力低下」とリハビリの決意
心臓の元気度を計る
経過観察のため定期的に通院し、その時にトレッドミルで心臓の状態を計る検査がありました。最初はゆっくりと進むのですが、ベルトの速度は徐々に上がり結構な早歩き状態に。その内に傾斜がかかり、坂を上る様な状態に。しかもベルトの速度も徐々に上がってくるので、脚の踏ん張りがないと直ぐにバテてしまいます。いや、最初の頃は心臓がそこまで持たないのです。
開始して間もなく医師から中止が告げられ、暫くの間は息も絶え絶え・・・情けない。これでは職場復帰しても通常勤務さえ耐えることが出来ません。直ぐには無理かもしれませんが、自宅でも体力回復のためのリハビリが必要だと痛感したのでした。
先ずは基礎体力をつける
何をするにも基礎体力がなければ何もできません。2週間程度の入院とはいえ、心臓という全身に血液を送るポンプを故障させたのですから、体力の落ち込みは想像以上に大きかったのです。しかも、退院当初はいつ心臓に異変が起きても不思議ではなかったため、「ニトログリセリン舌下錠(私が処方して貰っていたのはニトロペン舌下錠)」は肌身離さず持ち歩かなくてはならない必須アイテムとなっていました。
そんな中でもリハビリにより体力の回復を図らなくてはならないのです。
「どんなリハビリが良いのだろう?」
「そうだ!病院でのトレッドミル検査をクリアするためにウォーキングなどして徐々に体力を付けることにしよう!」
それでは、という事で屋外でウォーキングをすることにしました。
※医療的注意書き
なお、ここに記すリハビリや運動内容は、あくまで当時の私が主治医の指示のもとで行ったものです。心疾患の回復過程や運動負荷の許容範囲は個人差が大きく、自己判断で同様の運動を行うことは危険を伴う場合があります。
この続きは「心筋梗塞後のリハビリ体験記|退院直後のウォーキングと禁煙の壁をどう乗り越えたか」でお待ちしています。
無理のない範囲でお読みいただければ幸いです。